目次
- 企業が海外販売に抱く3つの誤解
- 実は今こそチャンス?海外市場を取り巻く最新動向
- 小さな企業が海外で選ばれる理由
- 越境ECという選択肢:中小企業に向いている理由
- よくある課題とその解決法
- まとめ〜最初の一歩を踏み出すには〜
少子高齢化や人口減少が進む中、国内市場の先行きに不安を感じる企業は少なくありません。これまでと同じやり方では成長が見込みづらくなり、新たな販路や顧客を求めて、海外市場への関心が高まっています。
その一方で、「海外販売は特別な企業だけができること」「多くの資金や人材がなければ難しい」といったイメージが根強く、実際に行動に移すには高いハードルを感じるケースも多く見られます。
しかし近年では、越境ECやデジタルインフラの進化によって、海外販売に挑戦しやすい環境が整いつつあります。物流、翻訳、決済といった壁をサポートするサービスも充実しており、これまで不可能に思われていた取り組みが、現実的な選択肢として再評価され始めています。
本記事では、海外販売の現状や課題、そしてそれを乗り越えるための考え方と具体的な方法について、最新の動向とともに解説します。
1. 企業が海外販売に抱く3つの誤解
海外販売への関心が高まりつつある中で、多くの企業が最初の一歩を踏み出せずにいます。その背景には、現実とは異なる「思い込み」や「先入観」が大きく影響しています。ここでは、特に多くの企業が抱きやすい3つの誤解を取り上げ、それぞれの実態を見ていきます。
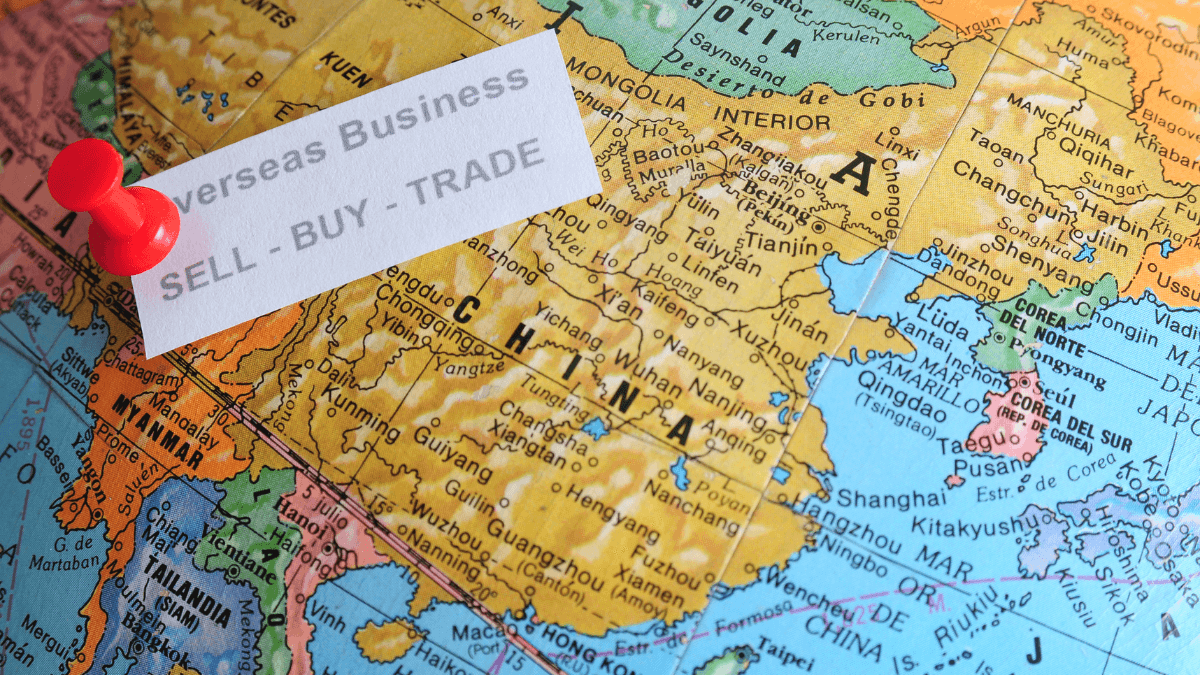
1-a. 誤解1.海外販売は大企業や有名ブランドだけのもの
「海外展開は知名度のある大手企業だからできることで、自社には無縁だ」と感じている企業は少なくありません。たしかに過去には、資金力やブランド力を武器にした大手企業が海外市場をリードしてきました。しかし、現在の越境EC市場では、その常識はもはや当てはまりません。
消費者のニーズは多様化し、SNSやレビューを通じて“知らなかったけれど魅力的な商品”を自分で探し出す時代になっています。むしろ大手では提供しきれない「個性」や「こだわり」が強みとなり、小規模な企業や地域のブランドが注目を集めるケースが増えています。
1-b. 誤解2.海外市場は遠くて難しい
文化や言語、商習慣の違いに対する不安から、「海外市場は複雑で手が出しにくい」と感じる企業も多くあります。しかし、近年のデジタルインフラの発展により、こうした障壁は確実に下がってきています。
たとえば、多言語に対応した越境ECモールを活用すれば、自社で翻訳やカスタマーサポートを抱える必要はありません。物流や通関も、専門業者による一括代行サービスが多数登場しており、国内販売とほとんど変わらない手間感で運用できる体制が整っています。
また、販売先として注目されている東南アジアや北米市場は、日本商品に対する信頼が厚く、「日本発ブランド」への関心も高まっています。心理的な距離のわりに、実際の市場との接続は思っている以上にスムーズです。
1-c. 誤解3.うちは国内でも手一杯で、海外まで手が回らない
限られた人数やリソースで事業を運営している企業にとって、海外販売は「新たな負担」だと感じられるかもしれません。実際に、新規開拓や業務拡張には工数がかかるため、後回しにされるのも無理はありません。
ただし、越境ECの強みは「小さく始められること」にあります。はじめから大規模な投資や現地法人の設立を目指すのではなく、まずは既存の商品を小ロットで出品し、市場の反応を見るといったアプローチも十分可能です。
最近では、サブスクリプション型の販売モデルや、受注後生産・受注後仕入れに対応したシステムも整ってきており、在庫リスクを抑えたまま海外展開を試すことができます。
2. 実は今こそチャンス?海外市場を取り巻く最新動向
かつては「海外に売る」と言えば現地法人の設立や代理店契約など、時間もコストもかかる大がかりなプロジェクトが前提とされていました。しかし、今ではその構図が大きく変わっています。デジタル技術と越境ECの普及により、中小規模の企業でも海外市場にアクセスできる環境が整ってきたのです。
2-a. 世界市場の拡大と日本製品へのニーズ
特に注目すべきは、東南アジア・中東・欧州・北米といったエリアにおける「日本製品」への関心の高まりです。背景には、日本の商品に対する信頼感や品質への評価があります。食品、日用品、文具、雑貨、ファッション、伝統工芸品など、いずれの分野でも“日本らしさ”を求める需要が根強く存在しています。
たとえば、アジア圏では健康志向・清潔志向から日本の食品や化粧品が好まれ、欧米ではシンプルで丁寧なデザインの商品が「ユニークで魅力的」と受け取られています。こうした現地の消費トレンドと自社商品の強みがマッチすれば、大手ブランドでなくても十分に勝負できる土壌があるのです。
2-b. ECとSNSがもたらす“知名度ゼロでも売れる”構造
近年はSNSやインフルエンサー、商品レビューといったクチコミ要素の影響力が非常に大きくなっています。フォロワー数千人のマイクロインフルエンサーが紹介した商品が、海外で一気に注目されるといった事例も増えています。
越境ECモールでも、検索キーワードや特集ページを通じて「たまたま出会った日本商品」が売れる構造が確立されており、「知名度がないから売れない」という考え方は、もはや過去のものになりつつあります。
2-c. 海外販売を後押しする支援や制度も拡充
日本政府や自治体、商工会議所、金融機関なども、越境ECを含む海外販路開拓を支援する取り組みを強化しています。補助金や専門家派遣、マッチング支援、無料の海外ECモール出品支援など、多くの制度が整備されており、利用ハードルも年々下がっています。
3. 小さな企業が海外で選ばれる理由
「海外で売れるのは、有名ブランドや大手企業の商品だけ」――そう思い込んでしまいがちですが、実際の市場ではその逆の現象が起きています。大きな組織では提供できない“個性”や“こだわり”を持つ小さな企業の商品が、海外の消費者から高く評価され、選ばれるケースが増えているのです。
3-a.「唯一無二」が価値になる時代
グローバル市場では、他と同じではないものにこそ価値が生まれます。大量生産・大量消費が当たり前だった時代から、多様性やストーリー性を重視する消費スタイルにシフトしてきたことが背景にあります。
たとえば、日本の地方で作られる職人の手仕事、家族経営で受け継がれる伝統の味、サステナブルな素材で作られた日用品など、小規模だからこそ実現できる「作り手の顔が見える」商品に共感し、購入する海外ユーザーは年々増加しています。
さらに、エシカル消費やローカル文化への関心の高まりによって、“知られていない日本”の魅力を求める動きも強まっており、大手では届けきれない領域に小さな企業が活躍できる余地があるのです。
3-b. 情報発信力のハードルが下がった
SNSや動画配信ツール、越境ECモールの出店サポート機能など、情報発信の手段がかつてなく充実しています。英語が得意でなくても、自動翻訳ツールや多言語対応のプラットフォームを活用することで、海外のユーザーに自社の商品や思いを伝えることができるようになりました。
また、商品ページにストーリーや開発背景を加えるだけでも、現地ユーザーの関心は大きく高まります。単なるスペック情報だけではなく、「なぜこの商品を作っているのか」「どんなこだわりがあるのか」といった背景が、競争の激しい海外市場での差別化要因になります。
3-c. “信頼される日本品質”を背景に
海外の消費者にとって、日本製品には「品質が高い」「丁寧な仕事」「安心できる」というポジティブなイメージが根付いています。これは企業規模にかかわらず、日本から発信される商品全体に対して抱かれている期待値です。
つまり、小さな企業でも“日本ブランド”の一端として期待される存在であり、実際にその期待に応えるクオリティを持っている商品が数多くあります。たとえば、「日本製のハンドメイド」や「地域素材を活かしたスキンケア商品」などが現地で高評価を得るのは、こうした文化的な信頼が背景にあるからです。
3-d. 必要なのは“規模”ではなく、“価値を伝える力”
海外展開において問われるのは、企業の大きさではありません。商品のもつストーリーや、顧客への誠実な姿勢、そして伝えるための一歩を踏み出す勇気です。情報発信や販売のハードルが下がった今、チャレンジのハードルは過去と比べて格段に低くなっています。
4. 越境ECという選択肢:中小企業に向いている理由
従来の海外展開といえば、現地法人の設立、取引先の開拓、海外展示会への出展といった手法が一般的でした。確かに効果的な手段ではありますが、時間もコストもかかり、限られたリソースしか持たない中小企業にとっては大きな負担となりがちです。そんな中、急速に広がりを見せているのが「越境EC(海外向けオンライン販売)」という選択肢です。

4-a. 越境ECとは何か?
越境ECとは、インターネットを通じて海外の消費者に商品を直接販売する手法です。自社でECサイトを構築して海外対応させるケースと、Amazon、eBay、Shopee、ZenPlusといった越境ECモールに出店するケースがあります。
中でも、モール型の越境ECは、すでに整備された集客力・決済機能・多言語対応などを活用できるため、越境ECに初めて取り組む企業にとっては、非常に現実的で効率の良い手段といえます。
4-b. 中小企業に向いている3つの理由
1. 初期投資が小さく、始めやすい
モール型の越境ECなら、自社でサイトを構築・運営する必要がなく、月額費用や手数料だけで出品を始められるサービスも多く存在します。初期投資を抑えたまま、テストマーケティング的に少量出品から始めることができます。
2. インフラがすでに整っている
モール側には、翻訳、決済、通関、海外発送などのインフラが揃っているため、出品者側がすべてを自前で用意する必要がありません。たとえば、商品情報を日本語で登録すれば、自動で多言語に翻訳されたり、注文が入ったら提携の物流業者が海外発送を代行してくれるなど、作業の負担を大幅に軽減できます。
3. 小規模でも集客力を借りられる
越境ECモールは、多くの海外ユーザーが訪れるプラットフォームです。自社で一から広告やSEOを行わなくても、モール内の検索結果やキャンペーン、特集ページを通じて商品にアクセスが集まりやすくなります。これにより、「無名でも、実力があれば売れる」環境が整っています。
4-c. 越境ECは「販路拡大の第一歩」
国内市場が頭打ちになっている今、新しい市場を試してみる選択肢として、越境ECは非常に有効です。はじめから多額の投資や大がかりな準備が必要なわけではありません。むしろ、小さく始めて、少しずつ学びながら進められるという点で、中小企業にとっては理想的な手段とも言えます。
5. よくある課題とその解決法
越境ECは中小企業にとって現実的な海外販路の選択肢ですが、実際に取り組むとなると多くの企業がいくつかの課題に直面します。ここでは、よくある課題を5つ挙げ、それぞれに対する具体的な解決策を紹介します。
5-a. 課題1:言語対応への不安
「英語ができない」「現地の言語に対応できる人がいない」といった理由で海外販売をためらうケースは多くあります。しかし、近年は多言語対応を標準装備した越境ECモールが増えており、自社で翻訳スタッフを抱える必要はありません。
たとえば、商品説明の自動翻訳機能や、問い合わせ対応を代行してくれるカスタマーサポートサービスを利用すれば、言語の壁は大幅に低くなります。また、文化的なニュアンスに不安がある場合も、現地経験のある翻訳者や外注サービスを使うことで適切に対応できます。
5-b. 課題2:海外発送や通関手続きが複雑
「発送手続きが面倒そう」「関税や通関がよく分からない」といった不安もよく聞かれます。特に通関では、必要な書類や現地の規制を理解していないと、遅延やトラブルにつながりかねません。
こうした課題に対しては、物流代行サービスの活用が有効です。商品を国内の倉庫に送れば、そこから梱包・国際発送・通関手続きまで一括して代行してくれるサービスもあり、EC業務と変わらない感覚で海外発送を実現できます。
5-c. 課題3:トラブル対応やクレームへの不安
「現地のお客様からのクレーム対応が不安」「トラブルになった時どうすれば?」という懸念も根強くあります。特に言語や文化の違いがあると、感情の行き違いが発生しやすくなります。
こうした場合は、モール側のカスタマーサポートや、外部の多言語対応CS代行サービスを活用するのが有効です。初期段階では、サポートの整ったプラットフォームを選ぶことで、トラブル対応を肩代わりしてもらうことができます。あらかじめFAQを多言語で用意しておくなどの工夫も、問い合わせの削減につながります。
5-d. 課題4:在庫・受注・決済まわりの負担
「在庫管理や注文処理が煩雑になりそう」「海外からの入金トラブルが不安」といった声もあります。しかし、越境ECモールでは決済・注文処理を自動化できる仕組みが整っており、国内ECと変わらない運用が可能です。
受注後に商品を発送する方式で運用すれば、過剰な在庫を持つ必要もありませんし、返品率の低い商品を中心にラインナップすればリスクもさらに軽減できます。また、多通貨決済や為替変動に強い決済ゲートウェイが提供されているため、支払いの確実性も担保されます。
5-e. 課題5:そもそも「何が分からないか分からない」
初めての取り組みでは、「まず何から調べればいいのか分からない」「誰に相談していいかも分からない」といった状態に陥ることがあります。これは実は多くの企業に共通する“第一歩の壁”です。
この場合、自治体や商工会議所、海外展開支援機関が実施している無料セミナーや個別相談会などを活用することが有効です。また、越境ECモールやサービス提供会社によっては、導入前の相談窓口や導入後の伴走支援体制が整っているところも多く、専門知識がなくてもスムーズにスタートできる体制が用意されています。
6. まとめ~最初の一歩を踏み出すには~
海外販売に興味はあっても、何から始めればよいか分からない――そう感じたら、まずは「小さく試す」ことが大切です。すべてを完璧に準備する必要はありません。まずは越境ECモールに1商品だけ出品してみる、あるいは海外向けのSNS投稿を始めてみるといった行動でも十分な第一歩になります。
また、自治体や支援機関によるセミナーや無料相談、ECモール運営会社の導入サポートなども活用すれば、専門知識がなくてもスムーズに進めることができます。
重要なのは、情報を集めすぎて動けなくなるのではなく、小さな行動を積み重ねること。試行錯誤の中から、自社なりの海外展開の形が見えてくるはずです。
▽海外販売の第一歩を踏み出したい方へ
物流・翻訳・決済の課題をまとめて解決できる「ZenLink」のオンライン説明会を開催中です。
専門スタッフが、越境ECの仕組みや導入ステップをわかりやすく解説します。


