目次
日本国内の市場が縮小する中、新たな販路として注目を集めているのがアメリカ市場です。
世界最大級の購買力を持ち、越境ECに対しても柔軟な消費行動をとるアメリカの消費者たち。今、そのチャンスを活かして海外売上を伸ばす日本企業が増えています。
この記事では、アメリカ市場が注目される理由や消費者のニーズ、売れ筋ジャンル、そして初めての越境ECに適した販売チャネルの選び方までを徹底解説します。
「何から始めればいいのか分からない」という方こそ、ぜひこの前編から読み進めてみてください。
▶ この続きはこちら: [なぜ今アメリカ市場なのか?日本企業が知っておくべき越境ECの最新事情と始め方(後編)]
1. なぜ今「アメリカ向け越境EC」なのか?
日本企業が海外市場への進出を検討する際、最も注目される国の一つがアメリカです。
越境ECの手法を活用することで、現地に店舗を構えなくてもアメリカの消費者に商品を届けることが可能になり、そのハードルは年々下がっています。
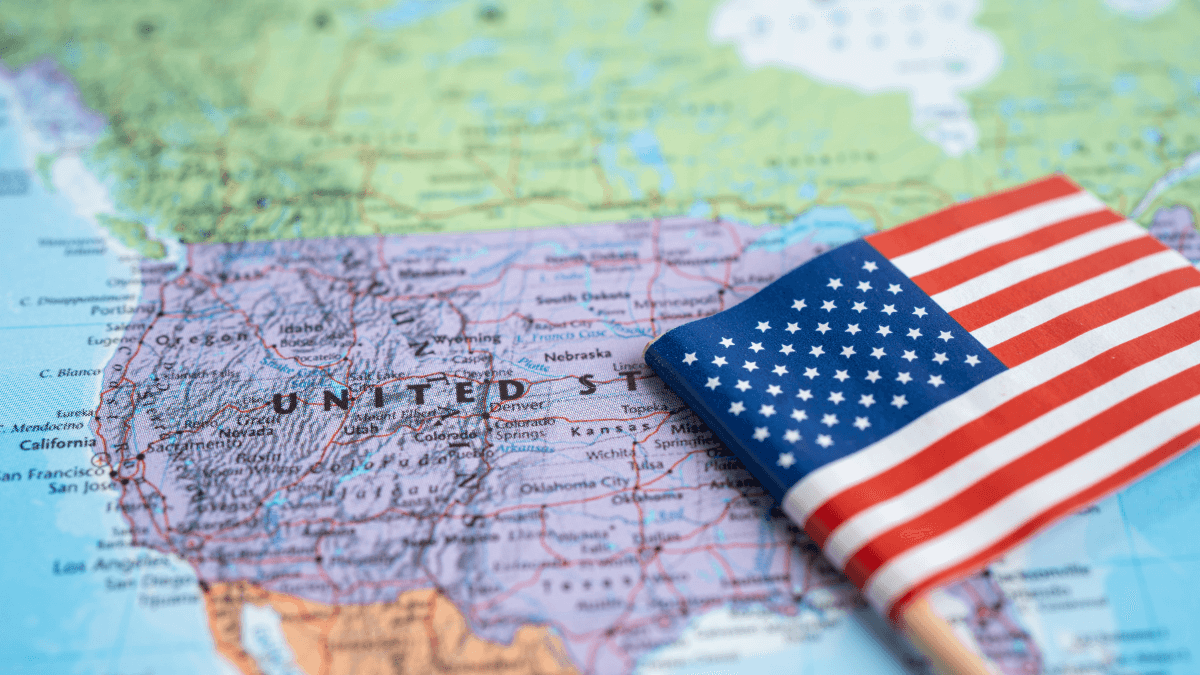
「なぜ今アメリカ市場に向けた越境ECが注目されているのか?」を明らかにするために、アメリカ市場の成長性、為替の影響、日本製品への需要、そして越境ECを後押しする環境や支援制度といった観点から掘り下げていきます。
1-a. アメリカ市場のEC化と成長性
アメリカは世界最大の消費市場を有し、EC(電子商取引)市場の規模も年々拡大しています。
Statistaによると、2024年時点でアメリカのEC市場規模は1兆ドルを超え、今後も着実な成長が予測されています。
参照:statista「eコマース-米国」
また、インターネットやスマートフォンの普及に伴い、オンラインショッピングの利用が生活の一部として定着しています。
注目すべきは、「アメリカ消費者の越境ECに対する抵抗感が低い」という点です。日本からの購入においても、「品質の高さ」や「日本ブランド」への信頼が強く、アメリカ向け越境ECにとって非常に好ましい環境が整ってきているのです。
さらに、アメリカでは日本と異なり、ブラックフライデーやサイバーマンデーといったセール文化が根付いており、それに合わせて購買行動が活発になります。これらの商機をうまく捉えることが、成功の鍵となります。
1-b. 円安と日本製品への関心の高まり
現在の為替状況も、アメリカ市場に対して越境ECを行う絶好のタイミングである理由のひとつです。円安傾向が続く中で、日本の商品はアメリカの消費者にとって「コストパフォーマンスが高い」存在になっています。たとえば、以前よりも少ないドルで高品質な日本製品が購入できるため、「今買っておこう」といった需要が生まれやすくなっています。
これは価格競争力を自然に確保できる状態を意味しており、まだアメリカ市場に進出していない中小企業にとっては、リスクを抑えて挑戦できるチャンスでもあります。
また、日本の伝統的な食品やアニメ関連商品、生活雑貨など、現地では手に入りづらい商材に対するニーズも強く、日本からの直送そのものが価値になる時代が到来しています。
1-c. 越境ECに追い風となる制度や支援施策
日本政府や各自治体も、越境ECを活用した輸出支援に力を入れ始めています。経済産業省をはじめとした公的機関が実施する補助金制度やセミナー、専門家の派遣などにより、以前に比べて越境ECのハードルは格段に低くなっています。
たとえば、日本貿易振興機構(JETRO)では、海外バイヤーとのマッチングや現地市場の調査支援なども行っており、初めてアメリカ向け越境ECに挑戦する企業でも、準備から展開までを段階的に進めることが可能です。
また、物流業者や決済事業者も、アメリカ市場向けに最適化された越境EC専用サービスを提供しており、「個人事業レベルでも海外販売ができる時代」になったといえます。
2. アメリカ市場の特徴と消費者ニーズ
アメリカ市場で越境ECを成功させるためには、単に「商品を売る」だけでなく、現地の消費者が何を求め、どういった価値観で購入を判断するのかを理解することが不可欠です。
ここでは、アメリカのEC消費者の特徴や、日本製品に対する評価、現地ニーズとのマッチングのヒントを紹介します。
2-a. どんな商品が求められているか?

アメリカ向け越境ECにおいて注目される商品ジャンルには、いくつかの傾向があります。
特に売れやすいのは、以下のようなカテゴリです。
- アニメ・キャラクター関連グッズ(フィギュア、ぬいぐるみ、文房具など)
- 美容・スキンケア商品(日本製フェイスマスク、敏感肌向けアイテムなど)
- 健康食品・サプリメント(抹茶、発酵食品、プロバイオティクスなど)
- 生活雑貨・文房具・キッチン用品(機能的かつデザイン性の高い商品)
- 伝統工芸品や地域の特産品(和紙製品、陶磁器、木製品など)
- これらの商品に共通しているのは、「日本らしさ」と「品質への信頼」です。アメリカ市場では、日本製品は「高品質
- 壊れにくい」「パッケージや細部の仕上げが丁寧」といったポジティブなイメージが広がっています。
一方で、ニッチな商品や、現地で手に入りにくい製品が逆に差別化要素となる場合もあります。「万人受けする商品」よりも、特定の層に刺さる個性のある商品が評価されやすいのが特徴です。
2-b. アメリカ消費者が日本の商品を好む理由
アメリカの消費者が越境ECを利用して日本の商品を購入する主な理由は、以下の通りです。
- 品質への信頼感:安全基準が高く、素材や製造工程にもこだわっていると認識されている。
- 独自性と文化的魅力:アニメや和食、伝統工芸など、日本独自の文化への憧れや関心が強い。
- 現地で入手困難:近隣店舗やAmazon.comには売っていないため、越境ECが唯一の入手経路となることも多い。
- ギフト需要:ユニークで高品質な日本製品は、誕生日やホリデーシーズンのプレゼントとしても人気がある。
特にZ世代〜ミレニアル世代の若年層を中心に、SNSなどを通じて「日本的なかわいさ(kawaii)」や「J-beauty(日本製美容)」がトレンド化しています。
SNSと連動したプロモーションが、購買に直結する傾向も強まっています。
2-c. 現地のトレンド・ライフスタイルとの相性
アメリカの消費者は、利便性・効率性を重視する傾向がありますが、それと同時に「エシカル消費」「サステナビリティ」「セルフケア」など、
新しい価値観を重視する層も増えています。これは日本の商品が得意とする分野と親和性が高い傾向にあります。
たとえば
- 無添加・オーガニック食品 → 健康志向と合致
- 長持ちする文具や雑貨 → 廃棄を減らしたい層に支持される
- 再利用可能なキッチン用品 → サステナブルなライフスタイルにマッチ
- 落ち着いた色合い・ミニマルデザイン → 洗練された暮らしを目指す層に響く
つまり、単に「日本からの商品です」と打ち出すだけでなく、現地の消費者の価値観やライフスタイルとどう結びつくかを伝えることが、商品訴求のカギになります。
3. 越境ECの始め方:3つの販売チャネル
アメリカ市場に向けて越境ECを始める際には、どの販売チャネルを選ぶかが初期段階の重要な意思決定になります。販売チャネルごとに、コスト・自由度・集客力・運用負荷などに大きな違いがあるため、自社のリソースや商品特性に合わせて最適な方法を選ぶことが求められます。
ここでは、主な3つの販売チャネルを紹介し、それぞれのメリット・デメリットを整理していきます。
3-a. 自社ECサイトを立ち上げて販売
自社でECサイトを構築し、直接アメリカの顧客に販売する方法です。ShopifyやWix、BASEなどを使って、越境対応のオンラインストアを立ち上げることが可能です。
メリット:
- ブランディングが可能: 自社独自の世界観・デザイン・コンセプトを表現できる
- 顧客情報を蓄積できる: リピーター戦略やCRMに活用できる
- 手数料が比較的安い: モールに比べて販売手数料が低く、利益率を確保しやすい
デメリット:
- 集客が難しい: 認知度ゼロの状態からスタートするため、SEOや広告、SNSが不可欠
- 運用負担が重い: 決済、翻訳、問い合わせ対応などをすべて自社で行う必要がある
- 信頼獲得に時間がかかる: アメリカの消費者にとって「無名サイト」への警戒感がある
適している企業:
長期的にブランドを育てたい企業、独自性のある商品を展開している企業、マーケティングにリソースを割ける企業。
3-b. Amazon・eBayなど現地モールに出店する
Amazon.comやeBay、Etsyなどの米国系ECモールに出店し、既存の集客力を活かして販売する方法です。
メリット:
- 集客力が非常に強い: 月間数億人規模のアクセスがあり、販売チャンスが豊富
- 信頼性が高い: プラットフォームのブランドがあるため、消費者の購入ハードルが低い
- 決済・物流の仕組みが整っている: フルフィルメントやカート機能がすでに完備
デメリット:
- 競合が多く価格競争に陥りやすい: 特にAmazonでは同一カテゴリでの差別化が必要
- 手数料が高い: 販売手数料、FBA(物流代行)費用などが収益を圧迫することがある
- ルール変更の影響を受けやすい: 出品制限やアカウント停止リスクも
適している企業:
すぐに売上を作りたい企業、在庫を多く持っている企業、人気商品・定番商品を販売している企業。
3-c. 卸売で現地小売と連携する
現地の小売店やディストリビューターに商品を卸し、販売は現地のECサイトや店舗に任せる方法です。いわゆる「BtoBtoC」の形態です。
メリット:
- 販売・顧客対応の負担が少ない: 最終的な販売は現地パートナーが担う
- 販路が広がる: リアル店舗や複数モールへの展開が可能になる
- 初期投資を抑えられる: ECサイト構築や広告費が不要
デメリット:
- マージンが少ない: 卸売価格になるため収益性が下がる
- ブランディングや価格コントロールが難しい: パートナー任せになる部分が多い
- 販路拡大のスピードに限界がある: パートナー探しにも時間とコストがかかる
適している企業:
自社で越境ECの運用が難しい企業、すでに一定量の生産体制が整っている企業、BtoBの経験がある企業。
3-d. チャネル選定のポイント
多くの企業では、「最初はモール出店でテスト販売 → 成功したら自社EC立ち上げ or 卸展開」といった段階的な戦略を取っています。
重要なのは、「すべてのチャネルを一気に展開する」のではなく、自社の強みとリソースに合わせて焦点を絞り始めることです。
また、チャネルごとに在庫・物流・販売管理の体制が異なるため、事前にシミュレーションを行うことが成功のカギとなります。
4. アメリカ向け越境ECにおける物流の設計
アメリカ向け越境ECにおいて、「どのように商品を届けるか」は、単なるオペレーション上の話ではなく、
顧客体験そのものを左右する重要な要素です。配送スピード、送料、返品対応などの物流体験は、購入の継続やレビュー評価に大きく影響します。
アメリカ市場を対象に越境ECを行う際の代表的な物流手段と、それぞれのメリット・デメリット、実務上の注意点について解説します。

4-a. 日本から発送する場合
最も手軽に始められるのが、「日本国内からアメリカの消費者に直接商品を発送する」方法です。発送方法としては、EMS(国際スピード郵便)やDHL、FedExなどの国際配送サービスが一般的です。
この方法のメリットは、在庫を日本国内に持てるため、商品管理がしやすく、受注後に発送することで在庫リスクを抑えられる点です。越境ECを初めて行う中小企業や、テスト販売を行いたい場合には適した手段といえるでしょう。
一方で、課題となるのが配送スピードと送料です。アメリカまでの配送には通常5〜10日ほどかかり、送料も商品サイズや重量に応じて高額になりがちです。また、関税が発生する場合には、受け取る側の顧客がその費用を負担しなければならず、トラブルの原因になることもあります。
4-b. アメリカ現地倉庫から発送する場合
本格的にアメリカ市場で販売を拡大したい場合は、「アメリカ国内の倉庫に在庫を預け、そこから配送する」現地発送型の物流が有効です。AmazonのFBA(Fulfillment by Amazon)やWalmart Fulfillment Services、Shopify対応の3PL(サードパーティ物流)などのサービスを活用できます。
この方法の最大の利点は、配送スピードが圧倒的に速いことです。アメリカ国内からの発送であれば、1〜3日程度で商品が届き、Amazonなどの大手並みの配送体験を提供できます。また、アメリカの消費者にとっては「国内から届く」安心感があり、購入の心理的ハードルも下がります。
一方で、事前にまとまった在庫を海外に送る必要があるため、在庫管理や売れ残りリスクが高くなるというデメリットがあります。輸送や保管の手配も複雑になるため、運用にはある程度の経験と資金的余裕が求められます。
4-c. 発送代行やフルフィルメントの活用
自社で物流体制を構築するのが難しい場合には、越境EC専用の発送代行サービスやフルフィルメントサービスの利用が現実的です。たとえば、国内にある発送代行業者に商品をまとめて預け、梱包から国際配送・通関までをワンストップで対応してもらう方法があります。
また、モール出店をしている場合には、FBA(Fulfillment by Amazon)などを使えば配送・返品・カスタマーサービスまでをすべて任せることができます。Shopifyのような自社ECサイトでも、対応可能な3PL業者と連携すれば、販売から配送までの一貫した運営体制が構築できます。
こうしたサービスを活用することで、少人数でも高品質な物流オペレーションが実現可能になります。
4-d. 返品対応と顧客満足度の両立
アメリカでは返品が非常に一般的な文化として定着しており、消費者は「とりあえず買ってみて、合わなければ返品する」という感覚を持っています。そのため、越境ECにおいても返品ポリシーの整備は避けて通れません。
対応方法はさまざまで、「返品不可」とあらかじめ明記するケースもありますが、これは評価の低下や購入回避につながるリスクがあります。よりスムーズに対応するには、現地倉庫や3PLに返品商品を返送できる体制を整えるか、日本国内で受け取って再販・廃棄を判断する仕組みが必要です。
近年では、返品ポリシーの自動化ツールや返品保険の導入も進んでおり、小規模な事業者でも負担を抑えながら顧客対応を行えるようになっています。


