目次
- なぜ今フィリピン市場なのか
- フィリピン市場の基本情報
- フィリピンEC市場の成長背景
- 主要ECプラットフォームと特徴
- フィリピンで売れる日本製品カテゴリ
- フィリピンの商習慣と文化背景を理解する
- フィリピン向け越境ECの課題
- 成功のための戦略とアプローチ
- SEOを活用した集客戦略
- 事例紹介|日本企業のフィリピン進出成功ストーリー
- まとめ:フィリピン向け越境ECで未来を拓く
東南アジアの中でもフィリピンは近年、急速にオンライン消費が拡大している国のひとつです。
スマートフォンを中心とした購買行動が定着し、ShopeeやLazadaなどの大手プラットフォームが市場をけん引しています。
さらに英語が公用語であるため海外からの参入ハードルが低く、日本製品に対する信頼度も高いため、事業拡大を目指す企業にとって注目すべき市場といえます。
本記事では、フィリピン市場の特徴や主要プラットフォーム、売れる商品カテゴリ、文化的背景、参入時の課題と戦略までを解説し、ビジネス展開を検討する際の参考になる情報を整理していきます。
1. なぜ今フィリピン市場なのか
フィリピンは人口約1億人を抱え、その多くが20〜30代の若年層で構成されています。
人口増加が続く一方で、経済も年率6%前後の成長を維持しており、中間層の拡大による購買力向上がオンライン市場の拡大を後押ししています。
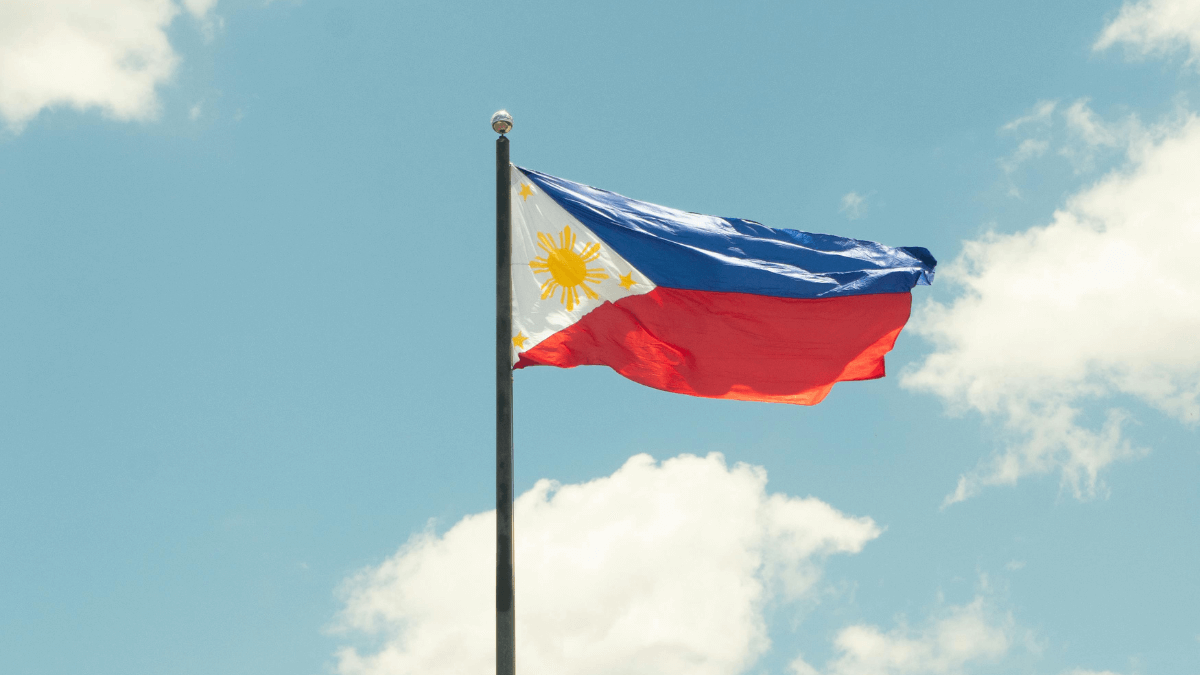
特に注目すべきはデジタル環境です。スマートフォン普及率の高さと決済・物流インフラの整備が進んだことで、オンラインショッピングが一気に日常生活に根付いています。加えて、英語が広く使われているため海外事業者にとって参入しやすく、日本製品に対しては、高品質かつ信頼できるといったブランドイメージが定着している点も強みです。
フィリピンの文化的背景も市場の魅力を高めています。多くの国民がキリスト教徒であり、クリスマスをはじめとする季節イベントの商戦期にはギフト需要が大きく膨らみます。このような人口動態、経済成長、デジタル環境、文化的要因が重なり、フィリピン市場は今まさに新しい販路開拓のチャンスが広がる舞台となっています。
2. フィリピン市場の基本情報
フィリピンは人口規模・経済成長・文化的背景のいずれにおいても、今後の消費市場拡大が期待される国です。
特に若年層の多さや中間層の台頭は購買力の底上げにつながっており、オンライン消費の広がりを加速させています。
家族志向やイベント消費といった文化的要素も加わることで、特定の時期に需要が一気に高まるなど独自の特徴が見られます。
フィリピン市場の規模や消費者の購買行動について整理していきます。
2-a. 人口・経済規模
フィリピンは東南アジアで有数の人口大国であり、2024年時点で1億1,000万人を突破しています。平均年齢は25歳前後と非常に若く、労働力人口の増加が今後も続くと予測されています。経済成長率は近年5〜6%を維持し、安定した拡大基調を示しています。都市部では中間層が増加しており、安定した収入を持つ層の購買力が市場を押し上げています。
2-b. 消費者特性と購買行動
フィリピンの消費者は価格に敏感ですが、単に安さだけを求めるのではなく、品質と価格のバランスを重視する傾向があります。日本製品は信頼性が高く、長持ちすると評価されており、やや高価格帯でも受け入れられやすいのが特徴です。
また、ソーシャルメディアの影響力が非常に強く、FacebookやTikTok、Instagramが購買行動の起点になっています。レビューや口コミ、インフルエンサーの発信がそのまま購買に結びつくケースも多く見られます。大家族文化が根強いため日用品のまとめ買いや季節ごとのギフト需要も高く、消費行動に独特のパターンを生んでいます。
3. フィリピンEC市場の成長背景
フィリピンのEC市場は、ここ数年で急速に拡大してきました。
その背景には、若年層を中心としたスマートフォンの普及、オンライン決済や物流インフラの整備、政府によるデジタル化推進の流れが重なっています。
加えて、コロナ禍をきっかけとした購買習慣の変化が、オンラインショッピングを日常的な行動として定着させました。こうした複合的な要因が市場の成長を後押ししており、今後も安定的な伸びが期待されています。

3-a. スマートフォン普及と若年層の購買行動
フィリピンは東南アジアの中でもスマートフォン依存度が高い国です。
多くの消費者がPCを持たずにスマホだけでインターネットを利用しており、ショッピングもそのままモバイルアプリ経由で完結します。特に20〜30代の若年層は新しいサービスへの適応が早く、セールやキャンペーンを積極的に利用する傾向があります。
3-b. 決済・物流インフラの改善とEC推進政策
かつてフィリピンでは、オンライン取引における決済手段の不足や配送の遅延が大きな課題でした。しかし近年は電子ウォレット(GCash、PayMayaなど)の普及や、銀行口座を持たない人でも使えるモバイル決済の浸透によって、オンライン決済の利用が一気に拡大しました。物流網の改善により、都市部を中心に配送スピードも向上しており、EC利用を後押ししています。政府もデジタル国家戦略の一環としてオンライン取引の普及を後押ししており、市場基盤が整いつつあります。
3-c. COVID-19によるオンライン購買習慣の定着
2020年以降のパンデミックは、フィリピンの消費行動を大きく変えました。外出制限や店舗閉鎖の影響で、これまでオンラインショッピングをあまり利用していなかった層も一気にデジタルに移行しました。その結果、「必要だから使う」から「便利だから使う」へと購買行動がシフトし、現在では日用品や食品を含め幅広い商品がオンラインで購入されるようになっています。
4. 主要ECプラットフォームと特徴
フィリピンのEC市場を理解する上で欠かせないのが、現地で利用されている主要プラットフォームです。ShopeeやLazadaといった大手マーケットプレイスが圧倒的なシェアを誇り、さらにTikTok Shopなど新興サービスも急成長しています。これらのプラットフォームは単なる買い物の場ではなく、プロモーションや顧客との接点としても重要な役割を果たしています。ここでは、それぞれの特徴を整理していきます。
4-a. Shopee(ショッピー)
フィリピンで最も人気が高いプラットフォームのひとつで、価格競争力と豊富なキャンペーン施策が強みです。「9.9」「11.11」など大規模セールイベントを仕掛け、消費者の購買意欲を引き出しています。アプリの使いやすさと積極的な割引戦略により、若年層を中心に広く支持されています。
4-b. Lazada(ラザダ)
アリババグループ傘下のLazadaは、東南アジア全域で存在感を持つ大手プラットフォームです。フィリピンでも利用者は多く、特に信頼性の高い配送や幅広い商品カテゴリが評価されています。大手ブランドの公式ショップも多数出店しており、安心して買える場としてのイメージが強いのが特徴です。
4-c. TikTok Shop
近年急成長しているのがTikTok Shopです。ショート動画やライブ配信を通じて商品を紹介し、そのまま購入につなげられる点が大きな魅力です。特に若年層の購買行動に直結しやすく、インフルエンサーやクリエイターを活用した販売戦略と相性が良いプラットフォームです。
4-d. その他(Zaloraなど)
ファッションに特化したZaloraは、都市部のトレンド志向の若者を中心に人気を集めています。EC市場全体でのシェアは大手ほど大きくはないものの、特定カテゴリでブランド力を発揮するプラットフォームとして存在感があります。
5. フィリピンで売れる日本製品カテゴリ
フィリピンの消費者は、日本製品に対して高品質で信頼できるというイメージを強く持っています。そのため、現地での販売実績も好調で、特に日常生活に密着した分野や若年層の関心が高いカテゴリが人気を集めています。
現地で需要が大きいとされる代表的な商品分野をご紹介します。
5-a. 美容・コスメ
日本の化粧品やスキンケア用品は、アジア全域で人気が高いジャンルです。フィリピンでも美白・保湿・ナチュラル成分といったキーワードが好まれ、現地ブランドとの差別化につながっています。口コミやレビュー文化が強い市場のため、SNSやインフルエンサーを通じた拡散が効果的です。
5-b. 食品・健康関連
インスタント食品や調味料、健康食品もフィリピンで注目を集めています。日本食ブームの影響でラーメンやお菓子といった商品は人気が高く、特に都市部では日本食レストランや専門店の利用経験がある消費者が多いため親和性が高いジャンルです。加えて、サプリメントや健康食品も信頼できる品質として評価されやすい分野です。
5-c. 家庭用品・育児グッズ
日用品やベビー用品も安定した需要があります。大家族が一般的なフィリピンでは、大容量や高耐久性を特徴とする日本製品が好まれます。特にベビーグッズや子育て関連の商品は、安全性や品質の高さを重視する消費者に支持されやすいのが特徴です。
5-d. デジタルガジェット・アクセサリ
スマートフォン関連のアクセサリや小型家電も若年層を中心に人気があります。スマホケースやイヤホン、モバイルバッテリーといった製品は日常的に需要が高く、流行やデザイン性を取り入れることで現地市場に適合しやすい分野です。
6. フィリピンの商習慣と文化背景を理解する
フィリピンでビジネスを展開する際には、単に市場規模や商品の需要を理解するだけでは不十分です。現地特有の文化や商習慣を理解し、それに沿った戦略を立てることで、消費者との信頼関係を築きやすくなります。
宗教的背景や家族志向、季節ごとのイベント需要は、購買行動に大きな影響を与えるため、商品選定やプロモーションの際に考慮する必要があります。

6-a. キリスト教文化とイベント消費
フィリピンは国民の約8割以上がカトリック教徒であり、宗教行事や祝祭が生活の中で大きな意味を持っています。特にクリスマスは9月から準備が始まるほど重要なイベントであり、この時期は消費活動が最も活発になります。プレゼント需要はもちろん、家庭内での食事や装飾に関する消費も増えるため、小売業にとって年間最大の商機となります。
6-b. 家族志向とギフト需要
フィリピン社会では大家族文化が根強く残っており、親戚や近しい人々とのつながりを重視する傾向があります。そのため、誕生日や結婚式、宗教行事などに合わせた贈答需要が常に存在します。日用品や食品、大容量パッケージの商品は家族で分け合えるものとして特に支持されやすく、日本製品の高品質・安全という価値がギフト需要とも結びつきやすい特徴があります。
6-c. クリスマス商戦の重要性
フィリピンのクリスマスシーズンは世界でも特に長く、9月から12月にかけて一大商戦が繰り広げられます。この期間は贈答用商品やプロモーションの需要が爆発的に高まり、事業者にとって最大の収益チャンスとなります。特に「限定商品」「ギフトセット」といった特別感を演出できる商品は、現地の消費者に強い訴求力を持ちます。
7. フィリピン向け越境ECの課題
フィリピンは成長市場として大きな可能性を秘めていますが、実際に事業を展開するとなるといくつかの壁に直面します。物流や通関の問題、現地言語や顧客対応の課題、さらには価格競争の激しさなど、戦略を立てるうえで注意すべき点が少なくありません。こうした課題を事前に把握しておくことが、持続的なビジネス展開を実現するための第一歩となります。
7-a. 物流コストとラストマイル配送
フィリピンは島国であり、国内の物流網が日本のように整備されていない地域も少なくありません。そのため、配送コストが高くなりやすく、特に地方へのラストマイル配送では時間がかかるケースもあります。消費者にとって配送の遅れは不満に直結するため、信頼できる物流パートナーの確保が不可欠です。
7-b. 関税・通関手続き
越境取引において避けられないのが関税や通関の問題です。書類の不備や規制への理解不足は、商品が通関で止まる原因となり、配送遅延や追加コストを発生させます。特に食品や化粧品など規制の厳しいカテゴリでは、事前に制度を把握した上で対応する必要があります。
7-c. 現地言語対応(英語・タガログ語)
フィリピンでは英語が広く使われていますが、購買層の多くはタガログ語やセブアノ語などを日常的に使用しています。そのため、商品説明やカスタマーサポートを現地言語で対応できる体制を整えることが、顧客満足度向上に直結します。英語のみでは十分に伝わらないニュアンスがあるため、多言語対応は競合との差別化要素にもなります。
7-d. 価格競争の激化
ShopeeやLazadaといったプラットフォームでは、多数の出品者が参入しており、価格競争が非常に激しい環境です。単純に安さで勝負すると利益を確保するのが難しくなるため、ブランド力や付加価値を打ち出すことが求められます。レビュー評価やプロモーション戦略も、価格以外の魅力を伝えるために欠かせない要素です。
8. 成功のための戦略とアプローチ
フィリピン市場は魅力的である一方、物流や価格競争などの課題も存在します。そこで重要になるのが、現地の文化や消費行動に合わせた戦略を柔軟に取り入れることです。単に商品を販売するのではなく、どのように現地の消費者に届け、信頼を得るかが成功の分かれ目となります。実際に成果につながりやすいアプローチを整理します。
8-a. ローカルインフルエンサーとの連携
SNSの影響力が強いフィリピンでは、インフルエンサーとのコラボレーションが有効です。現地の言葉で商品を紹介してもらうことで、購買のハードルを下げ、信頼感を高めることができます。特に美容や食品分野では、レビュー動画やライブ配信がそのまま購買につながるケースが多く見られます。
8-b. プロモーション(バウチャー、レビュー施策)
ShopeeやLazadaといったプラットフォームでは、割引クーポンや送料無料キャンペーンが購買意欲を大きく刺激します。また、レビュー文化が根付いているため、初期段階で顧客からの良質なレビューを獲得する仕組みを整えることが重要です。キャンペーンとレビュー促進を組み合わせることで、継続的な売上アップにつながります。
8-c. スマホ最適化とUX設計
フィリピンのECはスマートフォン経由の購入が中心です。そのため、商品ページや広告はスマホ画面に最適化されていることが必須条件です。表示速度、画像の見やすさ、決済手続きの簡便さなど、ユーザー体験(UX)を徹底的に改善することで、離脱を防ぎ購入率を高めることができます。
8-d. 段階的な市場参入モデル
初めから現地法人を設立して大規模に展開するのではなく、まずは越境ECでテストマーケティングを行い、一定の成果が得られてから現地倉庫や物流拠点を活用する段階的な戦略も有効です。リスクを抑えつつ市場理解を深めることで、長期的な成長につなげられます。
9. SEOを活用した集客戦略
フィリピン市場での販売を拡大するためには、プラットフォーム内での施策だけでなく、自社サイトやメディアを通じた集客戦略も重要です。その際に欠かせないのがSEO(検索エンジン最適化)です。現地消費者が検索するキーワードに対応した情報を発信し、適切に最適化されたページを運営することで、長期的な集客効果を期待できます。
実践的なポイントを整理します。
9-a. 関連キーワードの活用
まず重要なのは、フィリピン市場に関連する検索キーワードを明確にすることです。英語だけでなくタガログ語での検索も意識し、需要のあるフレーズをコンテンツに取り入れることで、現地ユーザーにリーチしやすくなります。例えば「Japanese cosmetics Philippines」「authentic Japanese food」といった検索は人気があり、日本ブランドの商品ページに誘導する効果が期待できます。
9-b. コンテンツマーケティングとSNS連動
SEO単体での集客には時間がかかるため、SNSとの連動が効果的です。ブログ記事や商品紹介ページを作成した際には、FacebookやTikTokで拡散し、外部からのアクセスを増やします。SNSからの流入が増えると、検索エンジン評価の向上にもつながり、長期的に上位表示を狙いやすくなります。
9-c. 内部リンク・外部リンク戦略
サイト内で関連ページを適切にリンクすることで、検索エンジンのクロール効率が高まり、評価が分散せずに集約されます。また、現地のメディアやブログ、インフルエンサーと提携して外部リンクを獲得することも、検索順位を上げる有効な手段です。特に現地サイトからのリンクは「ローカルで評価されている情報」としてSEO効果が高まります。
10. 事例紹介|日本企業のフィリピン進出成功ストーリー
理論やデータだけではなく、実際の成功事例を知ることは、フィリピン市場に参入する企業にとって非常に参考になります。ここでは、日本企業がどのように現地の文化や消費者特性を理解し、課題を克服して成果につなげたのかを紹介します。
10-a. 事例1:美容・コスメブランドの成功
ある日本の化粧品ブランドは、まず越境ECを通じて試験的にフィリピンで販売を開始しました。初期段階ではSNS広告と現地インフルエンサーを活用し、レビューや口コミを獲得することに注力。その結果、短期間でブランド認知が広がり、リピーターを獲得できました。その後は現地倉庫を活用して配送スピードを改善し、販売量をさらに拡大することに成功しました。
10-b. 事例2:食品メーカーの進出
日本食の人気を背景に、即席ラーメンやスナック菓子を販売する食品メーカーも成果を上げています。特に都市部では日本食レストランが多く、消費者が日本の味に親しんでいるため、オンラインでも受け入れやすい環境が整っています。同社は大容量パックやギフト向けセットを用意し、家族志向の強い文化に合わせた商品展開を行うことで売上を伸ばしました。
10-c. 事例3:育児・生活用品ブランドの展開
安全性と品質を武器にした日本のベビー用品ブランドは、フィリピンで着実に顧客基盤を拡大しています。現地の若い母親層をターゲットにSNS広告を展開し、安心して使える商品として認知を確立。レビューを積極的に集める戦略を採用したことで、消費者の信頼を獲得し、口コミによる自然な拡散も後押しとなりました。
11. まとめ:フィリピン向け越境ECで未来を拓く
フィリピン市場は、人口の多さと若年層の比率、そして経済成長の勢いを背景に、今後も大きな拡大が見込まれる注目のエリアです。スマートフォンを中心とした購買行動やSNS文化、さらに日本製品に対する信頼感といった要素が重なり、日本企業にとって有利な条件が揃っています。
一方で、物流コストや通関手続き、価格競争といった課題も存在します。しかし、現地の文化を理解し、インフルエンサー活用やプロモーション、スマホ最適化といった戦略を組み合わせることで、課題を克服しながら成果につなげることが可能です。
美容・コスメ、食品、日用品、ガジェットといった分野では、すでに日本企業の成功事例も生まれています。小さな一歩から始め、段階的に展開を拡大することで、リスクを抑えつつ安定的な成長を実現できるでしょう。
フィリピン市場は、単なる販路拡大の場ではなく、新たな顧客層と出会い、ブランドの可能性を広げるための大きなチャンスです。今後の事業展開を検討する中で、本記事で整理した情報が、次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。


