こだわりの素材を用い、価格にも妥協せずに服づくりを行うアパレルブランド「itochi」。
縫製や加工、仕上げまで、日本の職人や老舗工場が支える品質を徹底的に追求し、マニアックなほどの情熱で素材の魅力を引き出す服づくりを行っています。使われる生地には、すでに生産が終了したものや、次の供給が見込めず再生産が叶わないものもあります。
国内だけでは買い手が限られる——。そんな構造的な課題を見据え、越境販売を少しずつ拡大してきた中で、さらなる展開を支える仕組みとして「ZenLink」を導入しました。
こだわりを貫きながら、グローバルニッチを目指す「itochi」の挑戦について、代表・廣瀬雄太氏にお話を伺いました。

ー ブランド立ち上げの背景や、服づくりへのこだわりについて教えてください。
私はアパレル業界に入って20年近くになります。中堅規模のアパレルメーカーで、パタンナーや生産管理、数字を見ながらのものづくりも含めて、幅広く経験してきました。服づくりを突き詰めていくと、「世の中で“良い”と言われているもの」の、さらに上が存在するんです。そんな話を聞くと、つい好奇心が高まって、「ならば、それを使って服を作りたい」と思うようになった。それが、「itochi」を立ち上げたきっかけです。
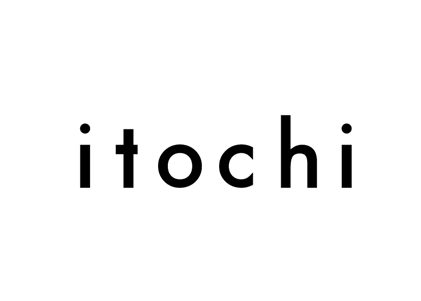
「itochi」ではすべてのアイテムで、国内の生産現場を巻き込んだ商品づくりをしているのですが、「日本製だから良い」と思っているわけではなく、服づくりを突き詰めた結果、そこに行き着いたという感覚です。
たとえば、玉虫色のプリーツスカート。ポリエステル100%なのですが、かなり特殊なつくりをしています。薄くて風で舞い上がるような生地なので、プリーツは機械では折れないんです。埼玉県の工場で、職人が専用の型紙に沿って1枚ずつ手で折り、スチーム釜で高温・高圧をかけて定着させています。

さらに、生地自体にもかなり工夫があります。この玉虫色の表現は、織物ならではの技術です。縦糸にグリーン、横糸にパープルと、それぞれに異なる色を使って織ることでしか出せない色合いで、紙やグラフィック、他素材では再現できない奥行きがあります。
すごく綺麗ですよね。でも、もう作れないんです。横糸に「カチオン染め」という特殊な染色方法に対応したポリエステル糸を使っているのですが、手間がかかりすぎるため、現在は廃番になってしまいました。そのため、残っていた400着くらいの分は、すべて買い取りました。それが終われば、この色のスカートは販売終了です。

ー 販売するうえでの課題はありますか?
最大の課題は、価格にあります。たとえば、この玉虫色のプリーツスカートは現在3万7,400円で販売しています。もし2万5,000円にすれば、日本市場では飛ぶように売れるはず。でも、それはやってはいけないと思っています。
なぜなら、それでは工場に支払う工賃が上がらない。すると技術の継承や、弟子の育成もできない。結果として“あと5年で消える技術”になってしまうからです。だから私たちは、「値段は下げずに、買ってくれる人を増やす」という選択をしています。つまり、グローバルニッチという戦略です。
「1つの国でメジャーになれなくても、複数の国でニッチであれば、全体として十分な市場規模になる」。私自身、この考え方にすごく共感しています。世界には、「大量生産の服では満足できない」「より良いものが欲しい」という人が必ずいると思っています。裾野を広げていくために、グローバル展開は必須だと考えてきました。
ー どのようにグローバル展開されてきたのですか?
最初に始めたのは、Instagram広告でした。主に台湾向けに広告を配信していたのですが、最初の1年くらいはまったく売れませんでした。それでも諦めずに広告出稿を続け、1年半ほど経った頃、同じ担当者名義・同じ住所(大阪)で複数の注文が入り始めて。「この人は誰なんだろう?」とずっと不思議に思っていたんですが、ある日、その方から「インボイス登録番号を教えてください」というメールが届き、それでようやく「うちの商品は、購入代行のZenMarket経由で海外に売れていたんだ!」と気づいたんです。
当時は他の越境ECサイトにも出店していたので、「なぜ購入代行経由なんだろう?」という疑問もありました。そこで、ECサイトで購入フローをひと通り確認してみたんです。すると、Instagramで興味を持っても、決済画面で不安になる。つまり、最後のひと押しで離脱していることが見えてきました。
そこで、カートページのフォームに「Address」「Postal Code」など、すべての入力欄に英語表記を併記してみたところ、購入代行を使わずに直接買ってくださる海外のお客様が増えてきました。台湾や香港、アメリカからも注文が入るようになったんです。
この経験から、高くても、うちの商品を「欲しい」と思ってくれる人は世界中にいる。必要なのは、信頼感や使いやすさといった最後のハードルをどう取り除くか、だったのだと気づきました。
ー その後、どのような経緯でZenlinkを導入されたのですか?
さらにグローバル展開を拡大させていきたいという思いがあったのですが、自分たちだけでできることには限界があり、難しさを感じていました。
ちょうどそのタイミングでZenLinkから提携のお話をいただきました。もともと購入代行のZenMarket経由でご縁があったので「ぜひお願いします」と導入を即決しました。
Zenlinkに特に期待しているのは、集客支援です。海外向けのメルマガやキャンペーン施策など、自分では手が回らない部分をプロに伴走してもらえるのは、本当にありがたいと感じています。
ー 今後の展望を教えてください。
現在、全体の売上に占める海外比率は5%ほど。これを将来的に30%まで引き上げたいと考えています。「売れること」は、単なる利益ではなく、技術や文化の継承にもつながる——そう信じています。
「良いものを作っている工場」が、目の前で次々と姿を消している。高コストゆえに買われず、廃業していく。この現実を、何度も目にしてきました。
たとえば、先ほどお話しした玉虫色のプリーツスカートのように、素材そのものが廃番になることもあれば、技術や工程ごと失われてしまうケースもあります。ライダースジャケットに使用していたウール素材も、愛知県・一宮市の工場で特殊な光沢加工が必要だったのですが、使用頻度に対して維持コストが重すぎるという理由で、2022年10月に加工機が廃棄され、もう作ることができなくなってしまいました。

さらに、スラックスに使用していた国産コーデュロイの生産も、現在は事実上の生産終了と言える状況になったと聞いています。日本でコーデュロイを作れる工場は現在国内に3社しかなく、後継者不足により現場に立てる人がもういなくなってしまったんです。
今この瞬間にも、技術は静かに消えている。そうした現実を、ただ見過ごすわけにはいきません。うちは小さなブランドですが、グローバルニッチな販売戦略を通じて、「良い商品が売れる」という流れをつくる。そして、結果的に産地や技術が守られる——そんな構造の起点となれたらと思っています。


